 |
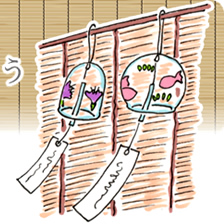 |
| チリンチリンと涼しげな音色と見た目で涼を誘う風鈴は日本の夏の風物詩ですね。 |
|

|
もともとは、中国の占いで使用されていた「占風鐸(せんぷうたく)」という道具が、仏教伝来と共に日本へ渡り、「風鐸」として伝えられ、お寺の境内の軒先に魔よけとして吊るされていました。 |
しかし、江戸時代に入ってそれまでの青銅製に加え、ガラス製も出回るようになると、風情を楽しむインテリアの一種として、どんどん庶民に広まっていきました。 |
日本の代表的な風鈴は2つあり「南部風鈴」は岩手県の工芸品で南部鉄器で作られていて透き通るような音色です。「江戸風鈴」はガラス細工で見た目の美しさと涼しげな佇まいが人気です。
東京都の西新井大師と神奈川県の川崎大師では、毎年7月に風鈴祭りが開催されています。 |

|
| 全国からたくさんの種類の風鈴が集まり、会場には美しい音色が響き渡ります。特に川崎大師は日本で最大級で約900種類の風鈴が集まるそうです。 オリジナルの厄除けだるま風鈴は名入れもしてくれるので毎年人気となっています。 |

|
どうして風鈴の音色は涼しげで心地よいのでしょう。それは科学的にも検証されています。
風の吹き方で変わる風鈴の音は、自然が作り出すゆらぎのリズムとなります。 また、風鈴の音色は日本人の心に刷り込まれている季節感と重なり、風鈴が揺れると脳が涼しいとイメージして抹消神経に伝達されます。実際に風鈴の音色を聴くと体温が下がったという実験データもあります。 |
窓を開けて風鈴の音色を聴きながらワイン。 心安らぐ村岡でした。 |
| |


